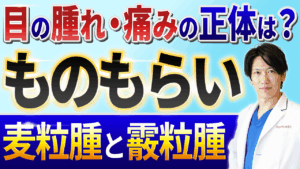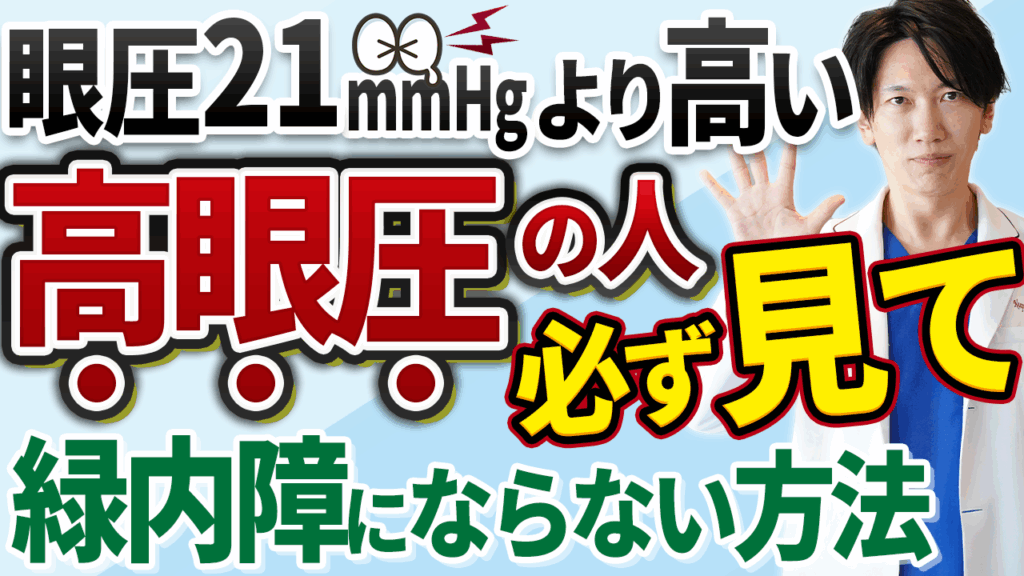
患者さんから「眼圧が高いと言われたのですが、これは緑内障なんですか?」「高眼圧はすぐ治療しないといけないのですか?」というご質問をよくいただきます。
今回は、当院の理事長・上月医師が対談形式でわかりやすく解説した対談動画もYouTubeでご覧いただけますので、ぜひあわせてご確認ください。
眼圧とは?まずは基本から
「眼圧」とは、その名のとおり「目の中の圧力」のことを指します。
私たちの目の中では、房水(ぼうすい)という液体が循環しており、この房水の量と流れによって、眼球内の圧力=眼圧が保たれています。
イメージとしては、水風船に近いものです。
- たくさん水が入ってパンパンに張っている状態が「眼圧が高い」状態。
- 水が少なくてふにゃっと柔らかい状態が「眼圧が低い」状態です。
通常、眼圧の正常値は10〜21mmHg程度とされており、21を超えると「高眼圧」と判定されることが一般的です。
高眼圧=すぐに緑内障、ではない?
「眼圧が高いから緑内障だ」と思ってしまう方が多いのですが、実はそう単純ではありません。
緑内障とは、「視神経(ししんけい)」がダメージを受けてしまい、視野が少しずつ欠けていく病気です。
眼圧はその大きなリスク因子ですが、「眼圧が高いから必ず緑内障になる」というわけではありません。
重要なのは、「その人の視神経が、その眼圧に耐えられるかどうか」です。
POINT
- 眼圧が25mmHgでも、視神経が強ければ緑内障にはならないことがあります。
- 一方で、眼圧が15mmHgと正常範囲でも、視神経が弱ければ緑内障が進行することがあります。
緑内障は「眼圧が高いかどうか」だけでは判断できません。
視神経がその眼圧に負けてダメージを受けているかどうかが問題です。
正常眼圧緑内障とは
日本人に多いのが、「正常眼圧緑内障」と呼ばれるタイプです。
これは、眼圧が正常範囲内(10〜21mmHg)にもかかわらず、視神経が徐々にダメージを受け、緑内障が進行していくタイプです。
日本人の平均眼圧は13〜14mmHg程度とされており、欧米人と比較して低めですが、それでも緑内障になる人は少なくありません。
このように、眼圧が正常かどうかだけで安心することはできないのです。
高眼圧症と緑内障の違い
高眼圧と緑内障はどう違う?
- 高眼圧症:眼圧は高いが、視神経に障害がなく視野も正常な状態
- 緑内障:眼圧にかかわらず、視神経が障害を受け視野が欠けていく状態
つまり、高眼圧症だからといって必ず緑内障になるわけではありません。しかし、将来的に進行するリスクがあるため定期的なチェックが必要です。
眼圧と緑内障の関係 ― ガイドラインからも確認できるポイント
日本緑内障学会がまとめた「緑内障診療ガイドライン(第5版)※外部リンクが開きます」によると、緑内障と眼圧の関係については以下のように整理されています。
- 眼圧は緑内障の最大の危険因子である
- しかし、眼圧が高い人すべてが緑内障になるわけではなく、逆に眼圧が正常範囲内でも緑内障になる人がいる
- 日本人では特に「正常眼圧緑内障」が多いことが知られている
つまり、単に「眼圧が高い・低い」で判断できるものではなく、視神経の強さや脆弱性、その他のリスク因子(年齢、家族歴など)を総合的に評価する必要があるのです 。
検査では何を調べるのか
緑内障の検査では、以下のような項目を調べます。
眼圧測定

眼圧を測定する方法には、いくつかの種類があります。
1つは、空気を目にプシュッと当てるタイプ。これは「ノンコンタクトトノメーター(非接触式眼圧計)」と呼ばれるもので、眼科を受診されたことのある方なら経験があるかもしれません。
この検査、目に突然空気が当たるため、苦手だと感じる方も多いです(得意という方のほうが少ないです)。ですが、このごく短時間の検査で、目の中の圧力(眼圧)を安全かつ正確に測定することができます。
視神経にかかる負担を知るためには、眼圧がどれくらいかを定期的に把握することがとても大切です。苦手意識があっても、ぜひ受けていただきたい重要な検査です。
もう一つは、目に直接測定器を軽く当てて計測するアプラネーショントノメーター(接触式)です。こちらは目に点眼麻酔を行ってから行います。
眼圧測定は緑内障の早期発見に欠かせないため、いずれの方法も医師が状況に応じて適切に選択しています。
OCT(光干渉断層計)

OCTとは「光干渉断層計(Optical Coherence Tomography)」の略で、目の奥にある網膜や視神経を、断層画像として細かく観察できる検査です。
まるでCTやMRIのように、目の中の構造を立体的に「スキャン」することができるのが大きな特徴です。
患者さんの中には「健診で眼底検査を受けたから大丈夫」と思われる方もいらっしゃいます。
確かに、健診などで行う眼底検査(眼底カメラ)は、目の奥の血管や網膜の表面を撮影するものです。糖尿病網膜症や高血圧性変化など、血管や網膜の異常を見つけるにはとても有用です。
しかし、緑内障の早期発見には眼底写真だけでは不十分です。なぜなら、眼底カメラで見えるのはあくまで表面的な部分であり、視神経がどれくらい薄くなっているか、繊維がどれほど減っているかまでは分からないからです。
OCTでは、視神経の厚みや構造をミクロン単位で測定できます。そのため、自覚症状の出るずっと前の段階で、神経のわずかなダメージを捉えることが可能です。
特に日本人に多い「正常眼圧緑内障」は、眼圧が正常でも神経が障害を受けているため、健診では見逃されてしまうことがあります。そこで、OCTを組み合わせることで初期の段階で発見できる可能性が高まります。
当院では、眼圧測定・視野検査とあわせてOCTを活用することで、より精度の高い診断と経過観察を行っています。緑内障が心配な方や、健診で異常を指摘された方は、ぜひ専門の眼科でOCT検査を受けていただくことをおすすめします。
(なお、OCTは眼圧検査とは違い風が出るような検査ではなく、光を見つめていれば撮影が終了するのでご安心ください。)
視野検査
視野検査は、「自分の見えている範囲=視野」がどれくらい保たれているかを調べる検査です。
緑内障では、見え方の中心からではなく、周辺視野から少しずつ欠けていくことが特徴です。しかし、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないまま進行するケースも多いため、視野検査によるチェックがとても重要になります。
ただしこの検査、実際に体験したことのある方からは「長くて疲れる」「集中力がもたない」と感じる方も多いです。片目ずつ行い、何度も小さな光を見つける作業を繰り返すため、苦手意識を持つ方も少なくありません。
さらに、実はこの視野検査の機械は、眼科によって機種や方式が異なるという点も知っておいていただきたいポイントです。

王子さくら眼科では、最新の視野検査機器『アイモvifa(アイモヴィファ)』を導入しています。この機器の特長は、両目を開けたまま、自然な姿勢でリラックスして検査を受けられるという点です。従来の視野検査と比べて疲れにくく、患者さんからも「これなら楽にできた」といった好評の声を多くいただいています。
視野検査は緑内障の進行度を把握し、治療方針を決めるための非常に大切な検査です。少しでも負担を軽くし、継続して受けていただけるよう、検査環境にも配慮しています。
緑内障かどうかは、上記のような様々な検査結果を確認し、医師が判断します。
緑内障は、自覚症状が出る頃にはすでに進行していることが多い病気です。
だからこそ、眼圧測定・OCT・視野検査を組み合わせることが、確実な診断と早期発見に直結します。
もしも緑内障と診断されたら?治療の目的と手段
緑内障と診断された場合、治療の目的は「進行を食い止める」ことです。
残念ながら、失われた視野は元に戻すことができません。
そのため、早期に発見して、進行を止めることが何より重要です。
主な治療法
- 点眼薬(目薬)
- 最も一般的な治療法。眼圧を下げることで進行を抑えます。
- 最近は種類も多く、症状に応じて複数を組み合わせることもあります。
- 参考リンク:緑内障の目薬にはどんなものがある?種類や効果、副作用について解説
- レーザー治療
- 非侵襲的(メスを使わない)で行える治療法です。
- 目の排水路の流れを改善し、眼圧を下げる効果があります。
- 参考リンク:レーザー治療
- 手術
- 点眼薬やレーザーでコントロールできない場合に行われます。
- 房水の流れを物理的に改善することで眼圧をコントロールします。
- 緑内障の手術は難易度が高いため、当院から紹介する際は信頼のおける医師への紹介状を書いています。
自覚症状がないからこそ、定期検査を
緑内障のもっとも恐ろしい点は「自覚症状がほとんどない」ことです。
ある日突然、「視野が欠けている」と気づいた時には、すでにかなり進行していることが多いのです。
そのため、「見え方に異常を感じてからの受診」では手遅れになってしまう場合もあります。
とくに40歳を過ぎた方、家族に緑内障の方がいる方は、定期的に眼科での検査を受けておくことが重要です。
まとめ 高眼圧は「要注意」。緑内障とあわせて経過観察を
高眼圧だからといって、必ずしも緑内障になるわけではありません。
しかし、リスクが高くなるのは事実です。
眼圧が高いと診断された場合は、以下の点を意識してください。
- 緑内障が進行していないかを定期的に確認する
- 必要に応じて点眼治療を行う
- 自己判断せず、専門医と相談しながら経過を見守る
緑内障も高眼圧症も、早期に発見し適切な対応をすることで、視力を一生守ることができます。
Youtube動画で更に詳しく
より詳しい内容は、ぜひ動画でもご覧ください。
目について気になること、不安なことがある場合は、お気軽に当院までご相談ください。
参考リンク
受診・予約案内
当法人は王子さくら眼科と経堂こうづき眼科、2院展開しております。王子さくら眼科は土曜祝日と開院しており、経堂こうづき眼科は土曜日曜祝日ともに行っているため、ご来院しやすい方にお越しください。
王子さくら眼科
〒114-0002
東京都北区王子1丁目10-17 ヒューリック王子ビル 5F
京浜東北線/東京メトロ南北線「王子駅」北口徒歩30秒 みずほ銀行の上
TEL:03-6903-2663
診療時間: 午前9:30〜13:00 午後15:00〜18:30
休診日:日曜日
王子さくら眼科予約について
webでのご予約も承っております。
web予約内での日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。
経堂こうづき眼科
〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ 2F
小田急線経堂駅すぐショッピングモール内
TEL:03-5799-7276
診療受付時間: 午前10:00-13:00 午後15:00-18:30
※木曜日休診、日曜祝日18:00まで
土日祝も診療を行っております。(木曜休診日)
経堂こうづき眼科予約について
一般診療の予約は受け付けておりませんので、直接ご来院くださいませ。
白内障手術の予約相談などを受け付けております。よろしければご家族の方も一緒にご来院ください。 webでの日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。
その他、予約できる診療内容については以下のリンクを御覧ください。
この記事の監修

上月 直之
こうづき なおゆき
医療法人社団慶月会理事長
日本眼科学会認定眼科専門医
所属学会
日本眼科学会
日本眼科医会
東京都眼科医会
日本白内障屈折矯正手術学会(JSCRS)
ICL研究会
日本緑内障学会
日本小児眼科学会・日本眼科アレルギー学会
日本角膜学会・ドライアイ研究会
オルソケラトロジー講習会修了
経歴
神戸大学工学部情報知能工学科 卒業
岡山大学医学部医学科 卒業
横浜市立市民病院 初期研修
慶應大学病院 眼科学教室
済生会中央病院 眼科
鶴見大学歯学部附属病院 眼科学教室
医療法人社団慶月会 理事長
日本眼科学会認定 眼科専門医
2018年 経堂こうづき眼科 開院
2021年 王子さくら眼科 開院
2022年 経堂白内障手術クリニック 開院
神戸大学と岡山大学で学び、慶應大学病院眼科学教室を経て、2018年に経堂こうづき眼科開院。日本眼科学会認定の眼科専門医であり、地域医療に貢献するとともに、最先端の医療提供に努める。最新の白内障手術を必要とされる方に受けてもらうため2022年経堂白内障手術クリニックを開院。