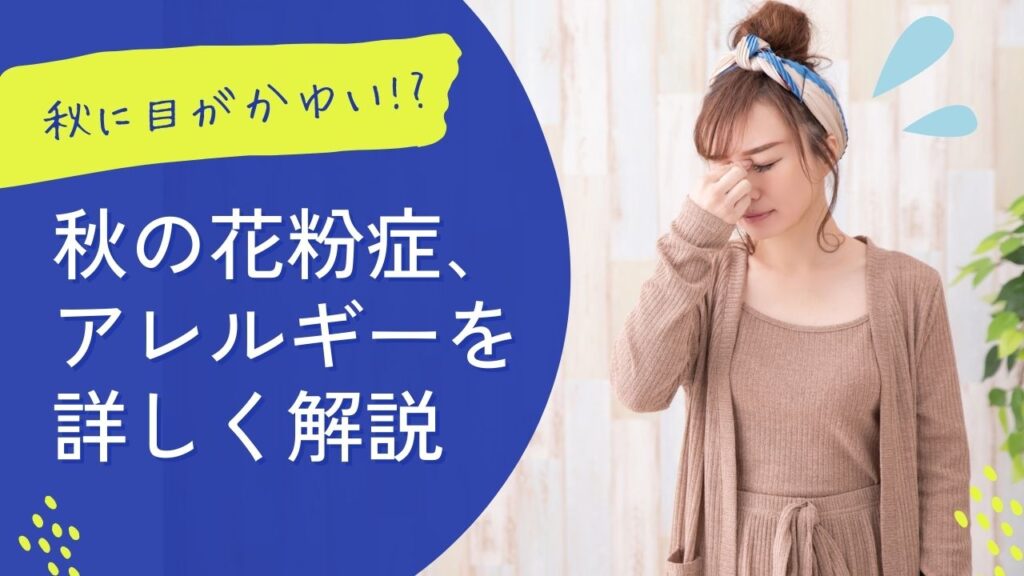
季節の変わり目の9月、10月、11月。くしゃみや鼻水が出る、目や鼻、喉や皮膚など全身がかゆい…。
中には、もしかして風邪かな?なんて感じられている方も多いのではないでしょうか。
もちろん季節の変わり目で朝昼の寒暖差が激しいこともあり、体調を崩しやすく、風邪を引かれる方が多い時期ではあります。
けれど、くしゃみや鼻水、目のかゆみの原因はもしかすると花粉症などの「アレルギー」かもしれません。
花粉症というと春のイメージが強いかもしれませんが、秋にも花粉は飛んでいますし、中には花粉以外がアレルギーの原因である可能性も。
今回の記事では、秋のアレルギーとその原因について解説していきます。
アレルギーって?

アレルギーは、通常は無害なアレルゲン(例: スギ花粉、ダニ、ハウスダストなど)が、身体の免疫系によって異物として誤認識されることから始まります。
この誤認識により、身体はアレルゲンを排除しようとして過剰に反応します。
アレルギー反応が起こると、免疫系はアレルゲンを排除するために特定の生物学的物質を放出します。その中でも、ヒスタミンという物質が主要な役割を果たします。
ヒスタミンは神経や毛細血管を刺激し、痛み、かゆみ、腫れ、発赤などの症状を引き起こします。
たとえば、くしゃみや鼻水、目の炎症や充血・かゆみは、ヒスタミンによる影響の一部です。
アレルギーの症状について

アレルギー反応の症状は、アレルゲンの種類や個人差によって異なります。
- 目のかゆみ、充血(アレルギー性結膜炎)
- くしゃみ、サラサラした鼻水、鼻づまり
- のどや皮膚のかゆみ、発疹や蕁麻疹
- 集中力の低下、だるさ、倦怠感、熱っぽさ
- 顔や体のほてり
以上が一般的な症状です。アレルギーの症状の程度は軽度から重度まで幅広く、中には喘息の症状が出る方もいます。
生活の質(QOL)に強く関わるため、症状が強くなる前の受診をおすすめします。
秋のアレルギーの原因と対策
秋の花粉症

春のスギやヒノキの花粉症が有名ですが、秋にも私たちの日常を脅かすアレルゲン、すなわち花粉が存在します。
その主な犯人は、都市の空き地や郊外に生息する雑草たちです。
ブタクサやヨモギといったキク科の植物や、カナムグラやカモガヤといった他の雑草たちが9月、10月、11月にかけての開花期に花粉を放出し、花粉症の原因となります。
中でもブタクサとヨモギは、日本全国で見かけるキク科の植物です。ブタクサは8月から10月にかけて黄色い花を、ヨモギは紫褐色の花を咲かせます。主に道端や公園、河川敷など、私たちの生活圏内に広く分布しています。
秋の花粉の対策
ブタクサやヨモギは、スギやヒノキよりも背が低いため、花粉の飛散距離は数十から数百メートル程度と限られています。このため、広範囲に花粉が飛散することは少なく、草原や川辺、土手など、ブタクサやヨモギの生えている場所・生えていそうな場所を避けることが最も効果的な対策となります。

さらに、外出時のマスクやメガネの着用も花粉症の症状を和らげるための有効な手段です。
しかし、ブタクサやヨモギの花粉粒子は小さいため、一般的な花粉用マスクではフィルタリングできない可能性があります。症状が強い場合は、PM2.5やウイルス対応のマスクを選択することで、より高い防護効果を得ることができます。
また、家の中に花粉を持ち込まないように、髪の毛や衣服をはたいてから家に入ることもおすすめです。洋服のブラシを使用するともっと効果的です。

ハウスダスト

ハウスダストによるアレルギーは通年性アレルギーと呼ばれ、一年を通してアレルギー症状を引き起こす原因となります。
実は、1年の中でも特に秋は最もハウスダストが増えやすい時期とされています。
ハウスダストとは、室内にたまるホコリのことを指し、この中にはダニの死骸やフン、カビなどが含まれています。中でもダニは、主に6月〜8月にかけての夏に繁殖するのですが、涼しくなると死んでしまいます。
これにより、秋になるとダニの死骸やフンが蓄積し、ハウスダストによるアレルギーになる方が多くなります。

他にも、秋は「衣替え」の時期でもあります。この衣替えが要注意。
久しぶりに洋服を取り出したところ、くしゃみが止まらなくなった、という経験をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
長い間クローゼットに保管していた洋服には、アレルギーを引き起こす繊維の残りやダニの死骸、フン、カビなどのハウスダストがついていることが多いです。特に閉じきった場所での収納は、これらの原因物質が増えると言われています。
衣替えをすると、こういったハウスダストが急に空気中に放出され、アレルギー反応を引き起こすことがあるのです。
ハウスダストアレルギーの対策

まずは、カーペットや寝具をこまめに掃除・洗濯することが大切です。
特にダニの死骸に関しては洗濯だけでは取れないことも多いため、掃除機をゆっくりと動かして隅々まで入念にかけることをおすすめします。ハウスダスト対策に特化した布団専用ノズルを使用するのもよいでしょう。
他にも、ダニは高い湿度を好むため、除湿機などで部屋の湿度を50%以下に保つようにしたり、定期的に布団乾燥機や天日干しなどで布団を乾かすことも対策に繋がります。
また、ダニは人のフケや垢、食べ物のカス、カビなどを餌として繁殖するので、お部屋をこまめに掃除し、定期的な換気・除湿を行い、寝具やカーペットを清潔に保つことが重要です。

次に衣替えの際の注意点ですが、重要なのは「なるべくハウスダストが空気中に飛散しないように行うこと」「ハウスダストを吸い込まないこと」「ハウスダストを室外に追い出す(換気する)こと」。
以下に衣替えの際の注意点をまとめます。
- なるべく丁寧に衣類を取り出す(ハウスダストを空気中に飛散させない)
- マスクを付けて衣替えを行う
- 窓を開け、十分に換気を行いながら衣替えをする
- 洗濯してしまっていたものも、出したときにもう一度洗濯・天日干しを行う
- これからしまうものもしっかりと洗濯・天日干しを行い(可能であればアイロンをかけるのも有効)、ダニ・虫除け・湿気取りと一緒に保管する
寒暖差アレルギー
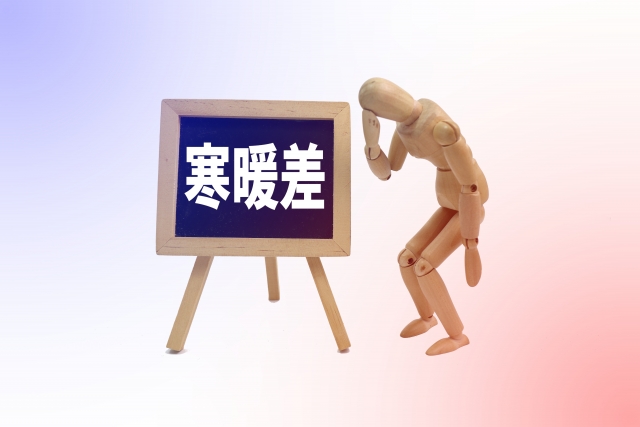
季節の変わり目や、朝晩と日中の温度差が大きくなることが原因で、くしゃみや鼻水が出る方もいらっしゃいます。
一般的に「寒暖差アレルギー」と呼びますが、医学的用語では「血管運動性鼻炎」と言います。花粉症などと違って明確なアレルゲンが存在しないためです。
温度差が刺激となり、鼻の粘膜の血管が広がり、粘膜が腫れることで症状が引き起こされると考えられています。
特に温度差が7度以上になると、寒暖差アレルギーの症状が出やすくなるとされており、自律神経のバランスの乱れが一因と言われています。
寒暖差アレルギーの対策

寒暖差アレルギーの対策としては、体温の調節と、自律神経を整えることが主になります。
体感温度の調整
体が感じる温度差を最小限に抑えることが重要です。外出する際には、軽く羽織れるアウターやマスクを携帯し、必要に応じて使用しましょう。
首元の保護
首には大きな血管が通っており、首を温めることで顔周りの血流が良くなります。スカーフやマフラーを使用して首を暖かく保つことがおすすめです。
マスクの使用
マスクを着用することで、冷たい空気が鼻や口に直接触れるのを防ぎ、粘膜の乾燥や刺激を軽減できます。
手首と足首の保護
手首や足首も大きな血管が通っている部分です。手袋や厚手の靴下を使用して、これらの部位を暖かく保つことで、全体の血流を良くすることができます。
刺激物質の回避
タバコの煙、排気ガス、香料などの化学物質や、精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱す可能性があります。これらの要因を避けることで、寒暖差アレルギーのリスクを低減できます。
筋肉の強化
筋肉量が少ないと、体温の調整が難しくなります。適切な運動、特に有酸素運動や筋トレを行うことで、筋肉を強化し、体温調整の能力を向上させることができます。
その他の理由
風邪 - 風邪とアレルギー性鼻炎の違い

秋は季節の変わり目であり、朝晩と昼の寒暖差が激しいシーズンのため、体調を崩されて風邪を引かれる方も多いかと思います。
そのため、自分のくしゃみの原因は花粉症などのアレルギーなのか、それとも風邪を引いているのかどっちなのだろう、と思われる方もいらっしゃるでしょう。
以下に、アレルギーが原因の場合と、風邪が原因の場合の違いについて記載します。
| アレルギーが原因 | 風邪 | |
| 原因 | 花粉、ダニ、ペットのフケ、カビなどのアレルゲンに体が過敏に反応することで発症します。 | ウイルスによって感染することで発症します。 |
| 持続時間 | アレルゲンに晒され続ける限り、症状は続く可能性があります。花粉の季節などは数週間から数ヶ月にわたって症状が続くことも。 | 通常、1週間から10日ほどで症状は改善します。 |
| 鼻水 | 透明で水っぽく、とめどなく流れます。 | 最初は水っぽい鼻水が出ることが多いですが、風邪の進行とともに黄色〜緑色ににごり、粘り気のある鼻水になります。 |
| 発熱 | ほとんどありませんが、微熱が出ることもあります。 | ほとんどの場合発熱を伴います。 |
| 目のかゆみ | 目のかゆみを伴います(アレルギー性結膜炎)。 | 目の症状はないことがほとんどです。(中には目の症状が出るウイルスもあります。詳しくはこちら) |
| 時期 | アレルギーの原因によって違いますが、花粉など季節性のアレルギーであれば毎年同じ時期に症状が出ます。例えばハウスダストなどが原因の通年性アレルギーであれば一年を通して症状が続きます。 | 季節は問いませんが、特に季節の変わり目や冬が多いです。 |
どちらにせよ、症状がひどい場合は一度病院の先生に相談されることをおすすめします。
乾燥

秋〜冬にかけて肌のかゆみが強い場合、「乾燥」が原因のことも考えられます。
秋から冬にかけては湿度が下がることも加えて、夏の紫外線の影響によって皮膚のバリア機能が低下しているため、肌が乾燥しやすくなります。また、夏と違って涼しくなり、こまめに水分補給をしなくなることも乾燥の原因となります。
保湿クリームなどでの保湿や、部屋を適切な湿度で保つことや、適度な水分補給が大切です。
もちろん、アレルギー症状+乾燥と、どちらも原因になっていることもあります。
症状が強い場合は、医師に相談するようにしましょう。
アレルギーの薬について
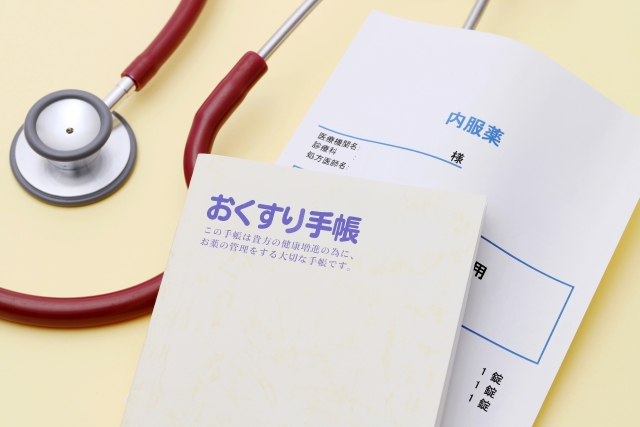
アレルギーの原因と対策について説明してきましたが、お薬でアレルギー症状を抑えることも重要です。
お薬を使ってかゆみなどの症状を軽くすることによって、アレルギーによる生活の質(QOL)の低下を防ぐだけでなく、アレルギーによるその他の病気を防ぐことにも繋がるからです。
たとえば、目のかゆみをそのままにして、目をかいたりこすったりするとかゆみが更にひどくなってしまいますし、他にも、かゆみを我慢して目を叩くことで網膜剥離が起こることもあります。
医師に相談し、ご自身の症状や体質に合ったお薬を処方してもらうことが大切です。なお、当法人の理事長上月直之は日本アレルギー眼科学会に所属しており、安心してアレルギーに関する相談を行って頂けます。
以下に、当院で扱うお薬の一部を挙げていきます。点眼薬・内服薬・点鼻薬・軟膏と項目に分けて説明します。
点眼薬(目薬)

処方薬の目薬には、主に「抗ヒスタミン」「ステロイド」「免疫抑制剤」の3種類の有効成分があり、主に処方するのは「抗ヒスタミン」の目薬になります。
「ステロイド」「免疫抑制剤」のお薬に関しては、症状が強い場合に医師の適切な管理の元で処方することがあります。今回紹介する成分以外に、市販の目薬にはこの他に「ケミカルメディエーター有利抑制物質」が含まれているものもあります。
なお、以下に紹介する点眼薬の中にはコンタクトを使用したまま点眼できるものもありますが、目の状態によってはそもそもコンタクトを使用しないほうがよい場合もあるため、詳しくは医師に確認してください。
抗ヒスタミン成分
- アレジオンLX点眼薬/アレジオン点眼液/*エピナスチン塩酸塩
- パタノール点眼液/*オロパタジン塩酸塩
- インタール点眼液
- ザジテン点眼液
*は後発医薬品(ジェネリック)
抗ヒスタミン成分は、アレルギー反応の主要な原因であるヒスタミンと競合し、ヒスタミン受容体に結合することでアレルギー症状を緩和します。これにより、かゆみや充血、涙などのアレルギー症状を抑える効果があります。多くの方にこちらの目薬を処方します。
ステロイド
- フルメトロン点眼液/*フルオロメトロン点眼液
- リンデロン点眼液/*ベタメタゾン点眼/サンベタゾン点眼液
*は後発医薬品(ジェネリック)
ステロイドは、強力な抗炎症作用を持ち、炎症を引き起こす物質の生成を抑制することで、アレルギー症状や炎症を緩和します。ステロイドは短期的に効果が高いため、重度の症状に対して使用されることが多いです。局所的な使用のため、副作用はほとんどありませんが、全くないわけではありません。医師の指導のもと適切に使用してください。
免疫抑制剤
- タリムス点眼液
- パピロックミニ点眼液
免疫抑制剤は、免疫システムの活動を抑えることで、アレルギー反応や自己免疫疾患による炎症を抑制します。これにより、慢性的なアレルギー症状や炎症をコントロールし、症状の改善を目指します。ただし、免疫抑制剤は免疫システム全体に作用するため、感染症のリスクが高まることがあるため、医師の指導のもと適切に使用することが大切です。重症の春季カタルなどに処方されることがあります。
点鼻薬

- ナゾネックス点鼻薬/*モメタゾン点鼻薬
- アラミスト点鼻薬
*は後発医薬品(ジェネリック)
現在の点鼻薬の主流はステロイド点鼻薬であり、副作用が少ないことが最大の特徴です。しかし、「ステロイド」という文字を見て、「強力」で「副作用が怖そう」と感じる方もいるでしょう。
アラミストやナゾネックスは鼻腔で作用し、ステロイド成分が血液循環に乗りにくいため、全身性の副作用は少ないです。
しかし、安全だからといって、副作用が全くないわけではありません。漫然と使用せず、適切な使用方法や期間を確認してください。
ステロイド点鼻薬は血管収縮点鼻薬のような速効性はないため、一度だけ使って終わりにする使用法では効果は期待できません。アナフィラキシー反応などの重篤な副作用が生じた場合は、速やかに医療機関を受診して適切な処置を受けてください。
内服薬(飲み薬)
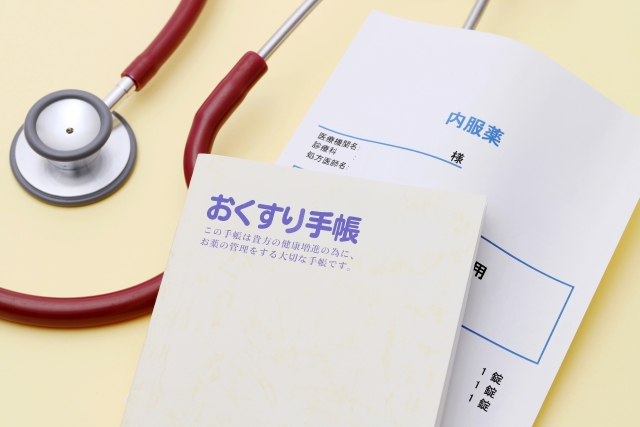
飲み薬を使用することでくしゃみや鼻水、かゆみなど、全身の症状を抑えることができます。
ただし、効き目の強さに応じて眠気などの副作用が出る場合があったり、薬によって飲む回数やタイミングが違うため、体質や生活習慣に合ったお薬を選ぶことが大切です。
なお、実際の効果や副作用には患者さんごとに違いがあるため、どれが自分の体に合うのかを試してみることが最も重要になります。
また、全身症状が強い患者さんには、ステロイドの内服薬(セレスタミンやリンデロン)が短期間のみ使用されることもあります。
「第1世代ヒスタミン薬」「第2世代ヒスタミン薬」「第3世代ヒスタミン薬」「漢方薬」に分けて説明していきます。
第1世代抗ヒスタミン薬
- クラリチン
効果はあるものの、眠気や口の乾きなどの副作用があります。市販薬に多く含まれています。
第2世代抗ヒスタミン薬
- アレロック/*オロパタジン塩酸塩
- ザイザル/*レボセチリジン塩酸塩
- アレグラ
- アレジオン
- ディレグラ
- タリオン
*は後発医薬品(ジェネリック)
病院で処方される主流の薬で、効果がありつつ眠気の副作用が少ないものが多いです。
特にザイザルは、効果と副作用のバランスが良いとされています。
第3世代抗ヒスタミン薬
- ビラノア
- ルパフィン
眠気の副作用がほとんどなく、効果も高いとされていますが、先発品のため値段が高いという短所があります。
漢方薬
- 小青竜湯
漢方薬の小青竜湯は、体をあたため、鼻水やくしゃみの原因である「水」の代謝を改善するとされています。そのため、花粉症などのアレルギーによるくしゃみや、サラサラした鼻水によく効く漢方です。
また、小青竜湯には眠くなる成分が含まれていないため、日常生活に支障をきたすことなく服用することができます。
小青竜湯は、抗ヒスタミン薬の内服と飲み合わせして頂いても問題ありません。
ただし「麻黄湯」という成分が入っているため、例えば「葛根湯」や「一部の風邪薬」などとの飲み合わせには注意が必要です。
飲み合わせに関して詳しくは処方時に医師や薬剤師に相談してください。
軟膏

花粉症は、主に鼻や目の症状が知られていますが、花粉が皮膚に触れることで肌荒れを引き起こすこともあります。この肌荒れは、アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎のような症状を引き起こすことがあります。肌荒れの治療・予防には、以下の軟膏が効果的です。
肌荒れの治療・予防には、これらの軟膏を適切に使用し、症状に応じて医師と相談しながら治療を進めることが重要です。
ステロイド軟膏
ステロイド軟膏は、炎症やかゆみを抑える作用があります。短期間で症状の改善が見込めるため、急性期の肌荒れや炎症に効果的です。副作用として、皮膚が薄くなることがあるため、使用は医師の指示に従ってください。
- プレドニン眼軟膏
- リンデロンA眼軟膏
- ネオメドロール眼軟膏(ステロイド+フラジオマイシン)
※フラジオマイシンに対するアレルギーをもつ患者さんが一定数存在することから、当院ではプレドニン眼軟膏を使用することが多いです。
免疫抑制軟膏
免疫抑制軟膏は、肌の免疫反応を抑えることで、炎症やかゆみを和らげます。ステロイド軟膏が効かない場合や、副作用が懸念される場合に使用されます。
- プロトピック軟膏
保湿用軟膏
保湿用軟膏は、乾燥した肌を保護し、水分を補給することで肌荒れを予防します。肌のバリア機能を強化し、外部刺激から肌を守ります。症状が軽度の場合や、予防目的で使用されます。
- プロペト
なお、上記で挙げたお薬は当院でよく処方するものになります。その他のお薬でご希望があればご相談ください。
まとめ
9月〜11月にかけての秋の季節にくしゃみや鼻水が出る原因として、風邪以外に「アレルギー」が考えられます。
春だけでなく、意外と秋にもアレルギーの原因となるものは多いため、症状が出た場合は早めに医師に相談されることをおすすめします。
また、アレルギーの症状が出る前から抗アレルギー薬を飲むことによって、症状が出てから薬を飲んだときに比べて症状を抑えることができます。
もしかして自分はアレルギーかも?と思った場合は、症状がない段階でも構いませんので、なるべく早く医師に相談するようにしましょう。
医療法人社団慶月会の理事長上月直之は、日本アレルギー眼科学会に所属しており、アレルギーに対する詳しい診療を行っております。
当法人は東京都内に北区王子の「王子さくら眼科」と世田谷区経堂「経堂こうづき眼科」2つのクリニックがありますので、ご都合に合わせてお選びください。
受診・予約案内
当法人は王子さくら眼科と経堂こうづき眼科、2院展開しております。王子さくら眼科は土曜祝日と開院しており、経堂こうづき眼科は土曜日曜祝日ともに行っているため、ご来院しやすい方にお越しください。
王子さくら眼科
〒114-0002
東京都北区王子1丁目10-17 ヒューリック王子ビル 5F
京浜東北線/東京メトロ南北線「王子駅」北口徒歩30秒 みずほ銀行の上
TEL:03-6903-2663
診療時間: 午前9:30〜13:00 午後15:00〜18:30
休診日:日曜日
王子さくら眼科予約について
webでのご予約も承っております。
web予約内での日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。
経堂こうづき眼科
〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ 2F
小田急線経堂駅すぐショッピングモール内
TEL:03-5799-7276
診療受付時間: 午前10:00-13:00 午後15:00-18:30
※木曜日休診、日曜祝日18:00まで
土日祝も診療を行っております。(木曜休診日)
経堂こうづき眼科予約について
一般診療の予約は受け付けておりませんので、直接ご来院くださいませ。
白内障手術の予約相談などを受け付けております。よろしければご家族の方も一緒にご来院ください。 webでの日程が合わない場合、予約なしで直接ご来院ください。
その他、予約できる診療内容については以下のリンクを御覧ください。
この記事の監修

上月 直之
こうづき なおゆき
医療法人社団慶月会理事長
日本眼科学会認定眼科専門医
所属学会
日本眼科学会
日本眼科医会
東京都眼科医会
日本白内障屈折矯正手術学会(JSCRS)
ICL研究会
日本緑内障学会
日本小児眼科学会・日本眼科アレルギー学会
日本角膜学会・ドライアイ研究会
オルソケラトロジー講習会修了
経歴
神戸大学工学部情報知能工学科 卒業
岡山大学医学部医学科 卒業
横浜市立市民病院 初期研修
慶應大学病院 眼科学教室
済生会中央病院 眼科
鶴見大学歯学部附属病院 眼科学教室
医療法人社団慶月会 理事長
日本眼科学会認定 眼科専門医
2018年 経堂こうづき眼科 開院
2021年 王子さくら眼科 開院
2022年 経堂白内障手術クリニック 開院
神戸大学と岡山大学で学び、慶應大学病院眼科学教室を経て、2018年に経堂こうづき眼科開院。日本眼科学会認定の眼科専門医であり、地域医療に貢献するとともに、最先端の医療提供に努める。最新の白内障手術を必要とされる方に受けてもらうため2022年経堂白内障手術クリニックを開院。






