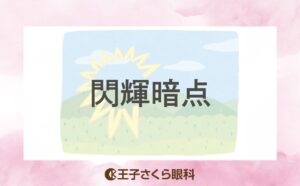網膜静脈分枝閉塞症
私たちの目の奥にある「網膜(もうまく)」は、カメラでいえばフィルムのような大切な部分です。網膜には細い血管がたくさん走っており、酸素や栄養を運ぶ役割をしています。ところが、この血管が詰まってしまう病気を「網膜静脈閉塞症(もうまくじょうみゃくへいそくしょう:RVO)」といいます。
RVOには大きく分けて2つのタイプがあります。
- 網膜静脈分枝閉塞症(BRVO):血管の一部分(分枝)が詰まるタイプ
- 網膜中心静脈閉塞症(CRVO):血管の根本(中心)が詰まるタイプ
分枝が詰まるBRVOよりも、中心が詰まるCRVOの方が重症になりやすいとされています。
なぜ起きるのか(原因)
血管が詰まる病気といえば「脳梗塞」や「心筋梗塞」がよく知られていますが、RVOもこれらと似た仕組みで起こります。
血液が固まりやすくなったり、血管が動脈硬化で狭くなったりすることで、血の流れが滞り、やがて詰まってしまいます。
特に以下の病気を持つ方はリスクが高いとされています。
- 高血圧
- 糖尿病
- 脂質異常症(コレステロールや中性脂肪が高い状態)
また、喫煙や不規則な生活も血管を傷め、RVOの発症に関わります。つまりRVOは「全身の血管の病気が目に現れたサイン」とも言えるのです。
主な症状
症状は詰まる場所や範囲によって異なります。
網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の場合
- 視界の一部がかける
- 物が歪んで見える(変視症)
- 視力の低下
BRVOは部分的な血管の閉塞なので、症状が軽いことも多く、中には自覚症状がなく健診の眼底写真で初めて見つかる方もいます。
網膜中心静脈閉塞症(CRVO)の場合
- 急に視力が落ちる
- 目の中に大きな出血が広がる
- 強い視力低下が長く続く
CRVOは網膜全体に血流障害が及ぶため、より重症です。場合によっては、視力が0.1以下にまで落ちてしまうこともあります。
検査方法
眼科では以下のような検査を行います。
- 眼底検査:瞳の奥をのぞいて出血の状態を確認
- OCT(光干渉断層計):網膜のむくみ(黄斑浮腫)があるかを調べる
- 蛍光眼底造影検査:点滴で造影剤を入れ、血流の流れを写真で確認
軽い場合は眼底検査とOCTだけで十分ですが、重症のときは造影検査まで行うことがあります。
治療方法
治療の中心は「むくみを減らす治療」と「異常な血管の発生を防ぐ治療」です。
① 抗VEGF薬の硝子体注射
- ルセンティス、アイリーア、バビースモなどの薬を眼の中に注射します。
- 黄斑浮腫を改善させ、視力の回復が期待できます。
- 効果は一時的なため、繰り返し注射が必要なこともあります。
② レーザー治療
- 血流が途絶えた部分(無血管領域)にレーザーを照射します。
- 「新生血管」という異常で弱い血管が増え、出血や緑内障を起こすのを防ぎます。
③ ステロイド注射
- むくみを抑える効果があります。
- 抗VEGF薬が効きにくい場合や費用面の理由で使われることもあります。
放置するとどうなる?
RVOを放置すると、次のような合併症が起こる可能性があります。
- 黄斑浮腫:網膜の中心がむくみ、視力が低下
- 増殖網膜症:新生血管が増えて網膜がダメージを受ける
- 新生血管緑内障:眼圧が急激に上がり、強い痛みと失明のリスク
特にCRVOでは、失明につながるケースも少なくありません。
日常生活で気をつけたいこと
RVOの治療はもちろん大切ですが、再発や悪化を防ぐためには生活習慣の改善が欠かせません。
- 血圧や血糖、コレステロールのコントロール
- 禁煙
- 適度な運動
- 塩分や脂質を控えた食生活
- 定期的な眼科・内科の受診
網膜の血管に問題が出るということは、脳や心臓の血管にもリスクがあるということです。RVOをきっかけに全身の健康管理を見直すことがとても重要です。
まとめ
- 網膜静脈閉塞症(RVO)は、目の奥の血管が詰まる病気です。
- BRVO(分枝閉塞)は部分的で軽症のこともありますが、CRVO(中心閉塞)は重症化しやすく注意が必要です。
- 主な治療は抗VEGF薬の注射とレーザー治療。繰り返しの治療が必要になることもあります。
- 放置すると黄斑浮腫や新生血管緑内障など、失明につながる合併症を起こすことがあります。
- 血圧や糖尿病、脂質異常など全身の生活習慣病が関わっているため、眼科だけでなく全身の健康管理が大切です。